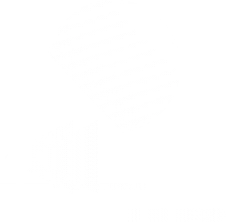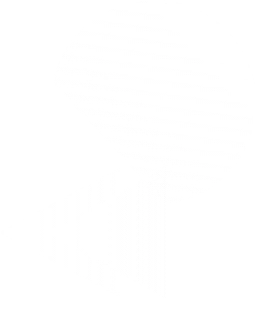ガスレビューコラム
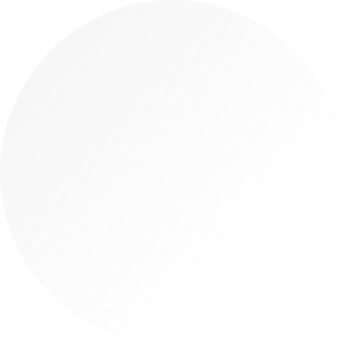
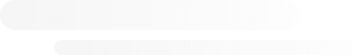
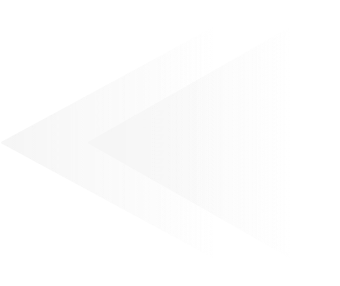
2025.04.07
産業ガス事業の特長
産業ガスとは、製造業をはじめ様々な産業プロセスで使われるガス体製品の総称であり、工業プロセスに使われる用途が多かったことから工業ガスとも呼ばれている。
主な産業ガスには酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、水素、ヘリウム、アセチレンなどがある。
そうした産業ガスを製造し、ユーザーサイドにデリバリーするのが産業ガス事業であり、そうした産業ガス事業を手掛ける企業群の事を産業ガス業界と呼んでいる。
産業ガス事業の特長について解説しよう。
産業ガス事業の特長
1 多様な用途
産業ガス事業の特長として、先ず「用途が多様である」ということが挙げられる。
鉄鋼、化学、自動車、ガラス、製紙、半導体などの電子部品をはじめ、あらゆる製造業の製造プロセスに使われている。
地球上で産業ガスを使わずに作られている工業製品はないといっても過言ではない程である。
では、何故、産業ガスがあまねく製造業で使われているかというと、産業ガス利用の目的が、大気成分を制御して製品品質や歩留まりを向上させ、生産効率を高めること、また、安全性を高めることにあるからである。
産業ガスは、ものづくりを支援する役割を担っている
詳しく説明しよう。
この地球上でモノづくりをするという事は、大気環境の中でプロセスを行うことに他ならない。
大気環境とは窒素80%、酸素20%、その他ガス成分は少しずつといった割合のこと。
しかし、製鋼プロセスで鉄鉱石を効率的に溶融するには酸素濃度が高い方が望ましい。
ガラス溶融炉では、窒素分がない酸素雰囲気下の方が、熱効率が高く燃料消費を抑えられる。
逆に精密部品である半導体製造では、酸素分があると製品品質に影響を及ぼす。
そこで不活性ガスである窒素雰囲気下でプロセスが行われている。
このように産業ガスは、プロセス中の雰囲気を最適化して、ユーザーのものづくりを支援する役割を担っている。
どんな産業でも自らのプロセスを最適化したいので、産業ガスを利用しているのである。
産業ガスを使うのは製造業だけではない。
病院で使われる医療用酸素は、病気やけがで一般の人より酸素を取り入れる力が落ちた患者さんのために酸素濃度を高めて吸入してもらうために使われている。
ポテトチップスなどの油菓子は大気雰囲気に晒しておくと酸化して味が落ちてしまう。
そこで、パッケージ内を窒素雰囲気にすることで酸化を防ぎ、風味を保持している。
2 好不況の波に左右されにくい
多様な用途を持つことは事業の安定性にも寄与している。
ある用途が不調であっても、その他の用途があることで事業が安定する。特定の業界に用途が偏っていないことがリスクヘッジになっている。
もちろん、産業ガスは主にユーザーのものづくりに使われるから、ユーザーの生産活動のアクティブさに業績が左右されやすい一面もある。
ただ、産業ガスの用途の中には、保安や防爆、パージといった安全など生産量に比例しないものもある。
さらにものづくり以外にも医療や食品、農業など産業活動とは異なる分野にも用途を持っているので、安定した事業性を有しているのである。
3 新規用途が生まれやすい
産業ガスは、世の中でイノベーションが起こり、新たな製品や技術が生まれる時、必ず新たな用途を生み出してきた。
これまでにも種々のイノベーションとともに新しいガス用途が生まれてきた。
そして、それは今後も続いていく。
人類の生存や文明の発展に貢献する産業ガス
今から100年以上前、鉄道の線路や橋梁などの鋼構造物を作るため鋼材を切断し溶接する必要が出てきた。
この時、酸素-アセチレンで鋼材を加熱・溶断するアプリケーションが生まれた。
このアプリケーションは、当時の最新技術であり、今も使われ続けている。
AIやデジタル化を支える半導体デバイスも、ガスによって進化を続けてきた製品である。
半導体デバイスは高機能化、大量生産とコストダウンを両立するために微細化、集積化といった進化を続けてきた。
その半導体デバイスの進化には、産業ガスの貢献が少なくない。
現在、人類社会が抱える温暖化による気候変動や人口増加による食料確保といった課題の解決にも産業ガスは貢献している。
人類が生存し、文明活動を続けていく限り、産業ガスの用途は拡大し継続していくのである。
4 世界中どこでも事業展開可能
産業ガスの主要製品(エアセパレートガス、酸素、窒素、アルゴンなど)は、大気を原料としているので、大気があるところ、すなわち世界中どこでも展開可能である。
どこでも展開可能という事は、出来る限り消費地近郊で製造し供給する方が良いともいえる。
産業ガスは消費地立地の商品であるといえる。
5 法規制が厳しい
世界中どこでも展開可能な産業ガス事業であるが、誰でも参入可能かというとそうではない。
ガス体製品であるため、産業ガスを安全かつ効率的に輸送、貯蔵するには高い圧力で貯蔵できる専用の容器が必要となる。
高圧ガスは取り扱い方を誤ると大きな災害につながる恐れがあるので、法的に規制対象となっている。
安全に取り扱うために、種々の規制をクリアしなければならない。
この保安規制をクリアしたものでないと高圧ガス事業を実施することはできない。
国によって規制の内容には違いがあるものの、法規制をクリアしたものだけが事業を行えるというところは共通している。
高圧ガス規制は、新規参入を妨げる参入障壁の一面もある。
日本には高圧ガス保安法という規制があり、これが海外からの新規参入の障壁として機能してきた一面もある。
新規参入が少ないことは既存事業者に有利に働く一方、競争が少なく、非合理な古い商慣習が残ってしまう一面もある。
6 設備産業であること
産業ガス事業には、大気から酸素や窒素を分離製造する深冷空気分離装置をはじめ水素や炭酸ガス・ドライアイスを原料ガスから分離精製する専用の製造設備が必要になるほか高圧化、または液化したガス体製品を安全かつ効率的に貯蔵しておく専用の容器が必要である。
産業ガス事業を展開するには、専用装置や容器といったインフラが不可欠で産業ガス事業は設備産業であるといえる。
そうした供給インフラをたくさん持っている事業者が、市場のイニシャティブを握るといえる。
従って、事業歴が長く、設備償却が完了しているインフラをたくさん持っている事業者の方が、新規参入者よりも収益面で有利に働く。
産業ガスの供給インフラの老朽化問題が今後の課題
ただ、近年の日本市場では、長年事業に供してきた供給インフラの老朽化が進展、更新の必要が出てきている。
もっとも、ガス販売量が横ばいで推移するとともに、インフレの進展で、素材価格や建設・工事費は上昇している。
販売量が伸びない環境の中で、如何に既存インフラを更新していくかという課題が生まれている
産業ガス事業の特長を要約すると
多様な用途
鉄鋼、化学、半導体、自動車、製紙、ガラスなどのあらゆる製造業
炭酸飲料、農業・食品、医療、環境改善などに用途あり
好不況の波に影響されにくい
多様な用途が補完関係
保安、パージ用窒素など生産量に影響うけない用途あり
新規用途が生まれやすい
新技術、新製品開発にガス利用はつきもの(例:EV、AI、脱炭素など)
世界中どこでも事業展開可能
エアセパレートガスの原料は大気であり、技術は共通なので、どこでも展開可能
法規制が厳しい
高圧ガス = 危険物、規制厳しい、新規参入を拒む
新規参入が少なく、古い習慣が残りやすい
設備産業であること
事業活動には深冷空気分離装置、高圧ガス容器などのインフラが不可欠
老朽化インフラの更新が課題