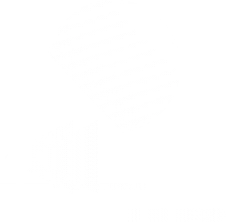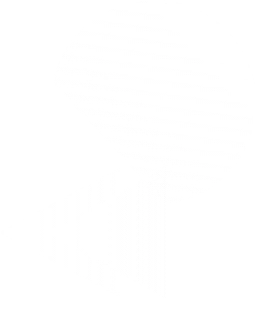ガスレビューコラム
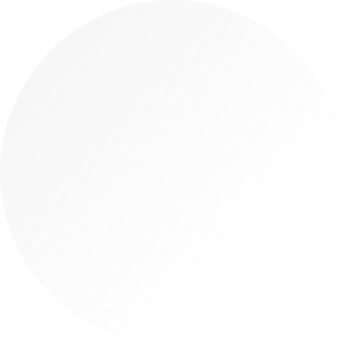
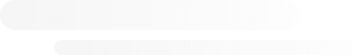
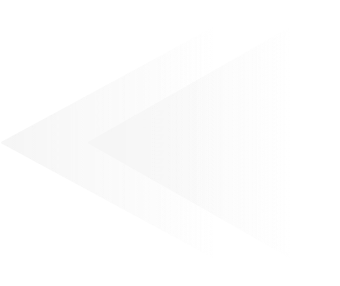
2025.04.21
食料増産に貢献する産業ガス
世界人口が増加していく中で、食料の安定確保は大きな社会課題である。
日本の食料自給率はカロリーベースで38%と言われているが、これを農作物の種や苗、家畜の飼料まで広げると自給率は10%近くに減少するという統計もある。
将来に亘って、安定した食料を確保していくことは日本にとって大きな社会課題の一つといってよい。
産業ガスもこの課題解決に資する役割を担っている。
ここでは食料の安定確保に貢献するガス利用技術について紹介しよう。
食料増産に使われる産業ガス
1 施設園芸でのCO2施用
先ず一つ目は農業分野、施設園芸でのCO2施用である。
これは植物の光合成に不可欠な炭酸ガス濃度を人為的コントロールして、収量の増大、成長の促進を図るというものである。
施設園芸とは、ハウス栽培のように密閉空間の中で温度や水、炭酸ガス濃度を制御する栽培法である。
植物の生育環境を人為的にコントロールすることで、収量アップ、収穫時期を調整するものである。
炭酸ガスで作物の収穫量をコントロール
炭酸ガス濃度コントロールに液化炭酸ガスを使用する。
ハウス内に炭酸ガスを流して炭酸ガス濃度を高め、光合成を促進させる。
小規模なハウスではシリンダー、植物工場と呼ばれる大規模なハウスでは、液化炭酸ガスのCEタンクを設置、ローリー車でガス配送を行っている。
炭酸ガス濃度コントロールの歴史は長く、日本においても1960年代に導入されていたが、当時は単に一定時間炭酸ガス濃度を高めただけで、収量アップなどの具体的な成果が得られず、一旦、ブームはすたれた。
その後、2000年代に入り、センサー類による精緻な環境コントロールが可能になったこと、加えて海外の大規模農園でのCO2施用の成果が認められはじめたことから国内でも再びブームとなっている。
課題は炭酸ガスのコストと収穫量のバランス
トマトや葉物野菜などでCO2施用が行われている。
CO2供給には暖房用のLPガスボイラーの燃焼排ガスを回収してハウス内に吹き込む方法もあるが、この方法だと暖房を使用しない季節に使えない。
液化炭酸ガスを使えば、最適な炭酸ガス濃度への調整が可能となるが、課題は炭酸ガスのコストである。
施設園芸の作物は、露地ものに比べ光熱費をはじめとする生産コストが余分に掛かっている。
コストを掛けた分、収量や収穫時期に付加価値を生まないと競争力はない。
炭酸ガスについても、なるべく効率的に使用したいわけで、光合成をおこなう葉裏の気孔周辺のみCO2濃度を高める局所施用を行うなどの工夫が行われている。
2 陸上養殖での酸素富化
もう一つの食糧増産への産業ガスの貢献は、陸上養殖での酸素富化である。陸上養殖とは、陸地に設置した水槽で魚介類を育成する手法のことであり、沿岸部をアミなどで隔離する海面養殖に対して設置場所を選ばず、高密度、成長促進、水質改善が図れる。
内陸のより消費地に近い場所で実施することで輸送コストを低減できるメリットがある。
近年では海面養殖の適地が減少していることから、収量が安定する陸上養殖を手掛ける事業者が増えてきている。
サーモン、ふぐ、ウナギ、ヒラメなどの陸上養殖が盛んになっている。
水槽内に人工的に酸素ガスを投入し溶存酸素濃度を高める。
酸素濃度が高い方が、魚の活性度が高まり、より多くのえさを食べて、早く大きくなる。
酸素供給法はシリンダーをはじめPSAや液など幅広い。
陸上養殖は地域を問わず全国的に広がりが期待できるガス用途であり、地域のガス事業者も注目している。